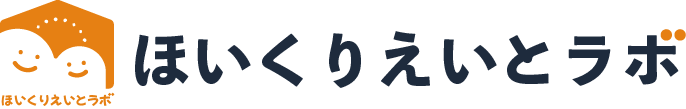いじめやハラスメントをどう考える?
学校や職場、サークルなど、人が集まるところではどこにでも、いじめやハラスメントの種があります。ほとんどの人は、道徳的な価値観だけでなく、利己的な感情を持っているからです。普段は、利己的な感情を抑えている人も、きっかけがあれば必要以上に他人を批判したり傷つけてしまうこともあります。ネット上の批判炎上などは代表的な例です。
職場で、いじめやハラスメントが起こるのは、利己的な感情の種が芽を出し、大きくなってしまう環境であるということです。そのような環境は、大きく以下の3タイプに当てはまります。
1.リーダーがワンマンで権力主義。組織自体がハラスメント体質になっている。
2.組織としての方針や評価基準が曖昧であり、現場の実情に合っていなかったり、職員に周知されていない
3.組織としての基盤はあるが、管理職のリーダーシップが発揮されておらず、現場の統率が取れていない。
いずれにしても、いじめやハラスメントが許容され見過ごされている環境です。閉鎖的になりやすい保育施設の職場では、長年の慣習が引き継がれていたり、職員間で序列や派閥が生じたりする場合も少なくありません。本来の組織の理念・目的を再認識し、組織としてどのような職員集団でありたいのかを今一度考え直してみましょう。
誰もが気持ちよく働ける環境づくりのために
いじめやハラスメントを未然に防ぎ、職員のメンタルヘルスを守るためには、透明性と心理的安全性の高い環境づくりが不可欠です。
- 明確な行動規範とルールの策定
- 「〇〇(ハラスメント)は許されない行為である」というメッセージを管理者が明確に発信し、ハラスメントの定義、相談窓口、懲罰規定などを周知徹底します。
- オープンでフラットなコミュニケーションの促進
- 職員が上司や同僚に対し、恐れることなく意見や不満を言える雰囲気を作ります。例えば、匿名での意見箱の設置、定期的な個人面談の実施、会議での発言を促すファシリテーションなどが有効です。特に管理者は、一方的な指示ではなく、職員の意見を傾聴する姿勢を示すことが、職場の心理的安全性を高めます。
- 管理職のマネジメント能力の向上
- 管理者は、ハラスメントが起こる前の小さなサインを見逃さない観察力と、問題が起きた際に毅然とした態度で公正に介入できるスキルを身につける必要があります。定期的にハラスメント防止研修などを実施し、全職員の意識向上と、管理職の仲裁能力強化を図りましょう。
職員が笑顔でなければ、子どもの笑顔も守れない
保育施設にとって、子どもたちが安心して過ごせる環境が重要であるのと同様に、そこで働く職員たちが安心して気持ちよく働ける職場環境の整備こそが、質の高い保育を実現するための最も重要な土台となります。
環境はすぐに変わるものではありませんが、現状を把握することがすべての対策の第一歩です。
貴園の職員の方々が、いま、どのようなストレスを感じ、どのような職場の課題を抱えているのか、その実態を正確に把握するために「ストレスチェック制度」の活用を強くお勧めします。これは法に基づいた制度であると同時に、職員の心身の状態を客観的に把握し、職場環境改善の具体的な手がかりを得るための最良のツールです。
弊社は、一般の職場環境とは異なる、保育施設に特化したストレスチェックを提供しております。ストレスチェック制度についてよく分からない、やってはみたものの職場改善のためにどう活用すればいいか分からないなど、お悩みがございましたらぜひご相談ください。